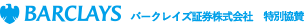第92回 2024年12月1日(日)『作曲のエポック』
バークレイズ証券株式会社 特別協賛
東京交響楽団&サントリーホール
「こども定期演奏会」
音楽は時代に乗って
第92回 「作曲のエポック」
2024年12月1日(日)11:00開演
サントリーホール 大ホール
ご挨拶 バークレイズ証券株式会社 代表取締役社長 木曽健太郎
「こども定期演奏会 2024」テーマ曲(山本菜摘 編曲)
小橋愛菜:『とびはねるシマエナガ』
Aina Kobashi (arr. Natsumi Yamamoto): Theme Music of “Subscription Concert for Children”
ワーグナー:楽劇『ニュルンベルクのマイスタージンガー』より
第1幕への前奏曲 *
Richard Wagner: Prelude to Act 1 from Die Meistersinger von Nürnberg
こども奏者*
[第1ヴァイオリン]網廣奏音(小学3年生)、野崎結翔(小学3年生)、伊藤藍凛(小学4年生)、瀬間 葵(小学4年生)、作田稜青(小学4年生)、三浦遙太(小学6年生)、酒井竣ノ介(中学1年生)
[第2ヴァイオリン]
土江賢吾(小学3年生)、平木大耀(小学5年生)、平瀬永崇(小学5年生)、岡本琥太郎(中学3年生)
[チェロ]龔 文薈(小学3年生)、龔 詩茲(中学1年生)、堀 菜乃(中学3年生)
[クラリネット]安藤麻奈美(小学4年生)
[ホルン]田中瑛大(小学6年生)
[トロンボーン]梁瀬莉央(中学2年生)
モーツァルト:オペラ『フィガロの結婚』K. 492 より 序曲
Wolfgang Amadeus Mozart: Overture from Le nozze di Figaro, K. 492
モーツァルト:オペラ『魔笛』K. 620 より 夜の女王のアリア「地獄の復讐はわが心に燃え」 **
Wolfgang Amadeus Mozart: “Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen”
from Die Zauberflöte, K. 620
ラヴェル:組曲『マ・メール・ロワ』より 第3曲「パゴダの女王レドロネット」
Maurice Ravel: No. 3 “Laideronnette, impératrice des pagodes” from Ma mère l’oye Suite
芥川也寸志:『交響三章』より 第3楽章
Yasushi Akutagawa: Trinita Sinfonica
III. Finale: Allegro assai
ストラヴィンスキー:バレエ音楽『春の祭典』~ロシアの異教徒の情景~ より「いけにえの踊り」
Igor Stravinsky: “Sacrificial Dance” from The Rite of Spring―Scenes of Pagan Russia
コルンゴルト:『キングスロウ~嵐の青春~』
Erich Wolfgang Korngold: Kings Row
指揮:沼尻竜典
Ryusuke Numajiri, Conductor
ソプラノ:肥沼諒子 **
Ryoko Koinuma, Soprano
東京交響楽団
Tokyo Symphony Orchestra
司会:坪井直樹(テレビ朝日アナウンサー)
Naoki Tsuboi, MC (Announcer of TV Asahi)
プログラム・ノート
「こども定期演奏会 2024」テーマ曲
小橋愛菜:『とびはねるシマエナガ』
小橋愛菜さん(小学5年生)からのコメント
真っ白なかわいいシマエナガが少しずつ成長していく姿を思いうかべて、この『とびはねるシマエナガ』を作曲しました。
最初は2匹のシマエナガが枝の上で楽しく遊びながら飛び跳ねているところから始まります。次は、羽ばたこうとしているけれどきちんと飛べずに、よちよちしている感じを表しました。最後は、ほかのシマエナガも集まって来て、みんなで一生懸命羽ばたいて、遠くに向かおうとしている様子を表現しました。
シマエナガのかわいい姿を想像して楽しい気持ちになってもらえたらうれしいです。
飯田有抄(クラシック音楽ファシリテーター)
本日のコンサートは「作曲のエポック」をテーマにお届けします。エポックとは、「時代」という意味の言葉です。クラシック音楽には400年以上もの長い歴史がありますが、どの時代も優れた音楽家たちは、かつてだれも聞いたことのなかった響きや、新しい時代を切り開く音楽を生み出してきました。
ワーグナー:
楽劇『ニュルンベルクのマイスタージンガー』より 第1幕への前奏曲
リヒャルト・ワーグナー(1813~83)は、オペラ(歌劇のこと)の世界に新しい風を吹き込んだドイツの作曲家です。それまでのオペラはおもに、登場人物を演じる歌手たちが、話すように歌う「レチタティーヴォ」と、物語の進行をいったんストップして心の中で思っていることをたっぷりと歌い上げる「アリア」とが、交互に出てくる形で作られていました。また、オーケストラは軽やかに歌の伴奏をするといった役割でした。しかしワーグナーは、レチタティーヴォとアリアの区別をなくして、歌手が朗々と歌い続け、オーケストラも立派に鳴り響く「楽劇」という新しい舞台芸術を考え出しました。『ニュルンベルクのマイスタージンガー』は、1868年に発表された3幕からなる楽劇です。靴職人で歌手のザックスが、若い騎士ヴァルターの歌の才能を伸ばし、歌合戦で勝たせてあげます。そしてヴァルターは美しい娘エーファとの恋が実るというハッピーエンドのストーリー。第1幕への前奏曲は、幕開けにオーケストラのみで演奏する堂々とした明るい音楽で、この楽劇の代表的な一曲です。
モーツァルト:
オペラ『フィガロの結婚』K. 492 より 序曲
続いては、1786年にヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756~91)が完成させたオペラ『フィガロの結婚』の序曲です。序曲も、オペラが始まる際にオーケストラだけで演奏する曲で、これから始まる劇のストーリーを予感させ、ワクワクするような音楽です。オペラの主人公は、伯爵の召使いフィガロ。もうすぐスザンナと結婚することになっていますが、女好きの伯爵が美しいスザンナを誘惑しようとします。困ったフィガロや伯爵の奥さんたちは、みんなで手を組んで伯爵をこらしめるという愉快な喜劇です。この劇には、身分の高い貴族に支配されてきた人たちが、いつまでも貴族の言いなりにはならないぞ!というメッセージが込められています。それを題材にオペラを作ったモーツァルトは、とても大胆で勇気がありますね。原作のお芝居は上演が禁止されたこともありますが、オペラでは問題になりそうなところをカットして、無事に上演が続けられた人気作です。
モーツァルト:
オペラ『魔笛』K. 620 より 夜の女王のアリア「地獄の復讐はわが心に燃え」
モーツァルトは35年という短い生涯のなかで、20作ほどのオペラを残しています。『魔笛』は1791年にモーツァルトが作った、彼の最後のオペラです。王子タミーノが、夜の女王の娘パミーナを救い出すため、魔法の笛を手にして、鳥捕りのパパゲーノと冒険するファンタジックなお話です。第2幕で、夜の女王が歌うアリア「地獄の復讐はわが心に燃え」は、娘のパミーナに敵を殺すように命じる場面の曲です。復讐の心をメラメラと燃やしている激しさが、音楽によく表れています。女王を演じるソプラノの歌手は、驚くほど高い音域まで使って見事に歌います。人間はここまで高い声で歌えるの?!とビックリするかもしれません。おそらくモーツァルトの時代の人々も、このアリアを聴いて興奮したことでしょう。『魔笛』の中でもっともよく知られる一曲です。
ラヴェル:
組曲『マ・メール・ロワ』より 第3曲「パゴダの女王レドロネット」
フランスの作曲家モーリス・ラヴェル(1875~1937)は、純真な子どもたちが大好きで、自分もまるで子どものように、機械仕掛けのおもちゃで遊んでいたそうです。1908年の夏、ラヴェルは親友夫婦がスペイン旅行に出かけるというので、彼らの子どもたちをあずかってあげることにしました。ミミとジャンという姉弟のために、ラヴェルはピアノ連弾の曲集を作ります。それが組曲『マ・メール・ロワ』です。『マ・メール・ロワ』(「マザー・グース」のフランス語)とは、昔から伝わるおとぎ話をまとめた童話集です。ラヴェルはその中から「眠れる森の美女」「親指小僧」「美女と野獣」などを題材にして作曲しました。「パゴダの女王レドロネット」は組曲の第3曲にあたります。パゴダとは、陶器でできた中国風のお人形のこと。パゴダたちが歌や楽器で、中国風の明るい音楽をかわいらしく演奏し、レドロネット姫にお聞かせしている様子を描いています。この美しい連弾曲集は、のちにラヴェル自身によってオーケストラ用に編曲されました。
コダーイ:
組曲『ハーリ・ヤーノシュ』より 第4曲「戦争とナポレオンの敗北」
組曲『ハーリ・ヤーノシュ』は、ハンガリーの作曲家ゾルターン・コダーイ(1882~1967)が劇音楽のために作った音楽から6曲を選び、1927年に組曲にまとめた作品です。ハーリ・ヤーノシュとは、劇の主人公の名前です。彼は、暴れ馬を見事に乗りこなしたとか、ナポレオンとの一騎討ちで勝ったとか、勇敢に戦った話を人々に語って聞かせますが、実はすべて農民である彼の作り話。組曲は、ハーリのファンタジックなストーリーを音楽で描いていきます。今日演奏される第4曲「戦争とナポレオンの敗北」は、ハーリとナポレオン軍との戦いの様子を、ピッコロ、アルト・サクソフォーン、トランペット、トロンボーン、テューバと打楽器で描いています。途中でフランス国歌「ラ・マルセイエーズ」風のメロディーが登場し、曲の終わりは、ハーリに負けたナポレオン軍がすごすごと退散するような葬送行進曲となります。
芥川也寸志:
『交響三章』より 第3楽章
『蜘蛛の糸』や『羅生門』などで有名な小説家・芥川龍之介の三男として生まれた芥川也寸志(1925~89)は、彼がまだ小さな頃に亡くなってしまったお父さんが残したレコードを聴いて、クラシック音楽に親しんできました。東京音楽学校(今の東京藝術大学)で作曲を勉強し、指揮者としても活躍した人です。『交響三章』は1948年、23歳の芥川が作ったオーケストラ曲です。1948年といえば、日本は大きな戦争で負けて3年しか経っていないころ。人々はみな暮らしを立て直そうと、一生懸命働いてがんばっていた時代です。芥川も音楽で仕事をしていこうと希望に燃えていました。この曲の第3楽章には、そんな芥川のエネルギーを感じることができます。力強い和音が打ち鳴らされて、まるで日本の祭囃子のように生き生きとしたメロディーが登場し、リズミカルに音楽が進んでいきます。
ストラヴィンスキー:
バレエ音楽『春の祭典』~ロシアの異教徒の情景~ より「いけにえの踊り」
続いては、ロシアの作曲家イーゴリ・ストラヴィンスキー(1882~1971)のバレエ音楽です。バレエといっても、可憐なバレリーナが華やかな衣装を身につけて、ふわりと舞うのとは大違い。ストラヴィンスキーが音楽を担当したこのバレエは、見知らぬ宗教の儀式を描いたもので、大地を讃え、若い女性のいけにえを神に捧げるという内容で、野生的で荒々しい表現に満ちています。1913年にフランスのパリの劇場でこのバレエが初めて上演された時、人々はあまりに聴き慣れない音楽や、体を震わせるようなバレエの振り付けや、不思議な衣装にびっくり仰天。客席は大声で笑ったり、ヤジを飛ばして大騒ぎ。一方で、ストラヴィンスキーの新しい音楽を「素晴らしい!」とほめる人もいて、お客さん同士が大げんかを始め、警察官が飛んでくる事態となりました。
「いけにえの踊り」はこのバレエの最後の曲で、拍子はめまぐるしく変わり、打楽器の荒々しいリズムや、金管楽器の刺すような響き、弦楽器の複雑な和音が響きます。
コルンゴルト:
『キングスロウ~嵐の青春~』
おしまいは、20世紀に映画音楽の世界で活躍した作曲家エーリヒ・ヴォルフガング・コルンゴルト(1897~1957)の音楽です。『キングスロウ~嵐の青春~』は、1942年に公開のアメリカ映画で、小さな街キングスロウに生まれ育った若者たちの愛や友情、社会を生き抜く厳しさなどを描いた物語です。キャストとして、のちにアメリカ大統領となったロナルド・レーガンといったスターたちが出演しています。コルンゴルトの音楽は、輝かしいオーケストラ・サウンドを響かせ、雄大さや、ほのぼのとした美しさにあふれます。冒頭を聴いただけでも、彼がいかにその後のハリウッド映画の音楽に大きな影響を与えているかが感じられることでしょう。
コラム
作曲のエポック~新しい音楽とは?
時代に新しい風を吹かせる画期的な発明や活動などをすることを「エポック・メイキング」と言います。今日のプログラムに登場するモーツァルトやワーグナーらはみな、新しい響きに満ちた音楽を書き残した人たちです。「エポック・メイキング」な作曲家とは、たんに誰もやっていなかったことや、真新しいことをしてきただけではありません。勝手に真新しい言葉を自分で作って話しても、誰にも何も伝わらないのと同じように、音楽もそれまで受け継がれてきたものを一切かえりみずに、勝手に音を並べたとしても、ただのひとりよがりになってしまいます。
では、新しい音楽、エポック・メイキングな作品とは、どのようなものなのでしょうか。それはきっと、その音楽を聴いた人たちが、何か新しいものの見方ができ、想像力を掻き立てられ、味わったことのない感情を発見できるものと言えるかもしれません。そうした音楽は、必ずしもわかりやすいものや、美しくて感動的なものとは限りません。それらは時に、人々にショックを与えて怖いと感じさせたり、不気味なものだと思わせたり、マイナスの感情を引き起こすこともあります。
今日のプログラムにあるストラヴィンスキーの『春の祭典』は発表された当時、まさにそのような反応を人々から引き出しました。しかしこの曲は、リズムの面白さや、爆発するような和音など、当時としてはとても新しい表現に満ちていて、その後の作曲家たちに大きな影響を与えました。作曲から100年以上も経つ作品ですが、みなさんはどう感じられるでしょうか。かっこいい? 怖い? おもしろい? 不思議? 音楽はどんな受け止め方をしても自由です。これまで味わったことのない気持ち、見たことのない風景が見えたなら、それはみなさんにとって新しい音楽の体験です。素晴らしいエポック・メイキングの瞬間なのです。
(文 飯田有抄)